
大徳寺の思い出に因んで
「膠漆(こうしつ)の交わり」
___離れがたいほど固い間柄のこと
この言葉は、中国後漢の時代『後漢書』「雷義伝」にある、雷義(らいぎ)と陳重(ちんちょう)が互いに才能を認め合い、地位も譲り合うほどの深い友情で結ばれていたという故事によるものだそうで、その様子を膠(にかわ)と漆に置き換えた人物の感性を感じる。『後漢書』の著者は范曄(はんよう)らしいが、言葉を作った同一人物かどうかは知らない。
古くから接着などに使われてきた膠(にかわ)とは、動物の骨や皮を煮出して作られ、日本画や工芸品の修理などにも適したもので、べっ甲色が美しい。
一方漆は、木から採取される油で、一定の温度と湿度帯に置くことで数千年残るほど強い塗膜を作る。膠と漆は自然界にある中で最も接着力の強い素材である。
歴史上、人間関係は国や世界を左右するほどの影響を持ってきたが、茶の湯にまつわる本を読んでいるともちろん例外ではないと感じる。そこには公家、武将、僧侶、商人、町人など数え切れないほど多くの人々が登場する。人生を左右するほどの真剣なやりとりが繰り広げられ、非業の最期を迎えた人も少なくない。
最も好きな映画の一つ『千利休 本覺坊遺文』の中で、織田有楽斎が「腹を切らなくては茶の湯者になれぬのか」と利休を始め先立った多くの人々を思い浮かべる。
そんな時代の中であったからこそ、膠漆の交わりと呼べるほどの関係もまた数多くあり、今に残る文化が生み出されてきたのではないだろうか。
二十年ほど前、恩師に連れられて大徳寺の真珠庵に伺った。恩師とご住職(当時)とは長年のお付き合いだったそうだが、その日は久しぶりの再会だったと見え、晩秋の肌寒い堂内で温かいお薄をいただきながら、ひととき懐かしい昔の話をされていた。互いにご高齢であるお二人は別れ際「今生の別れになるかもしれないね」と穏やかに言葉を交わされていたのが忘れられない。綿々と続く歴史を受け継ぐ場所柄、その印象はなお深い。
表立って頻繁な行き来がなくとも、久しぶりの再会でも心が通い合い、淡い交わりのように見えて膠漆の結びつきがある、自分にもそのような存在がたとえ一人でもいてくれれば、十分に幸せな人生といえるかもしれない。
漆に触れながら、そんなことを考えている。
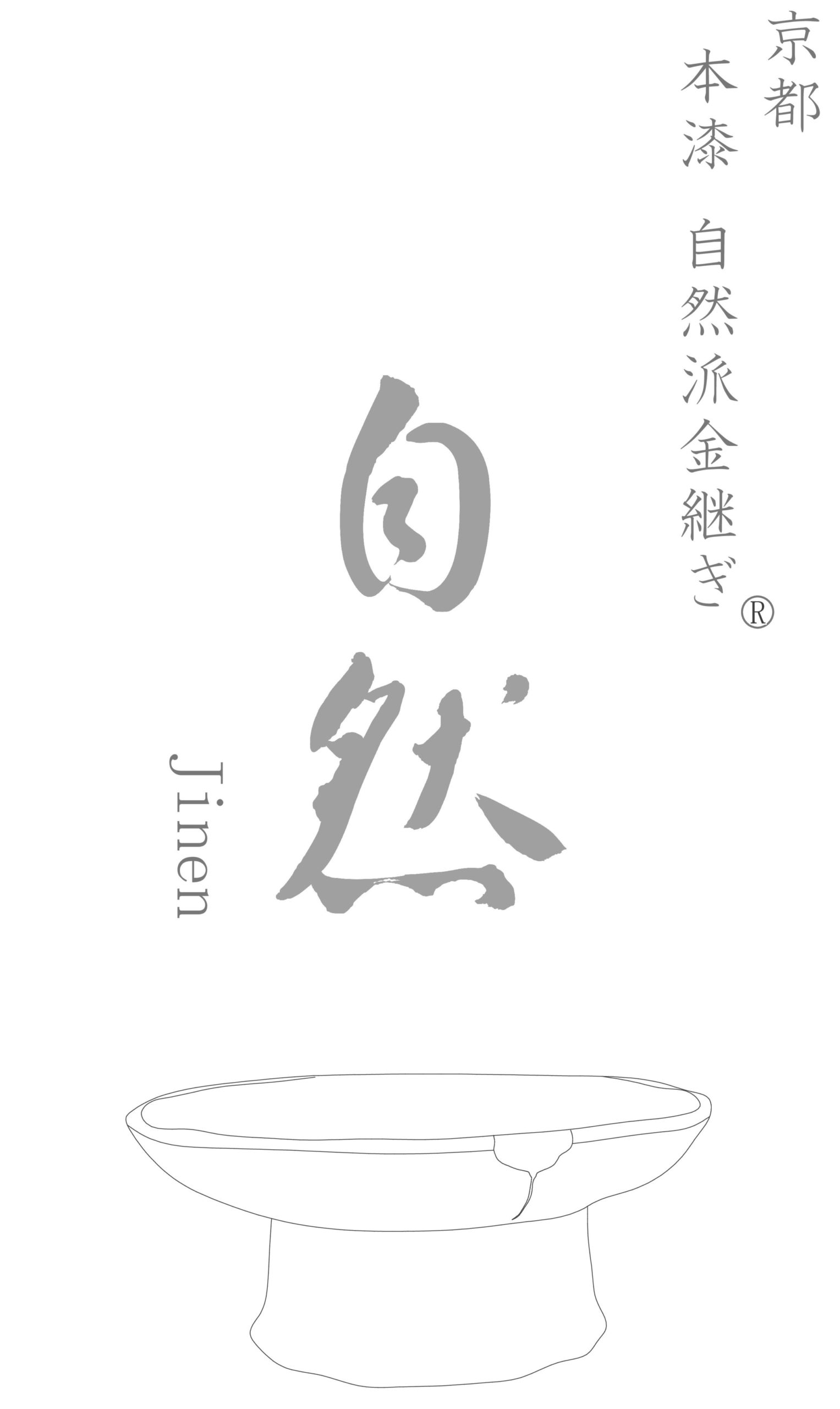
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。